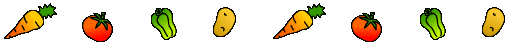お母さんの作ってくれたお人形は、お子さんにとって特別な存在です。先日も、中学に通う娘が
捨てようとして整理していた箱のなかから、昔、私が手作りした簡単な作りの人形をめざとく見
つけだし、「お母さんがこれ作ってくれたよねぇ。」と、感慨深げに言ったものですから、結局捨て
られずに、またしまい込んでしまいました。
せっかく作ったパペットです。お子さんにとって、すてきな幼児期の思い出になりますように、
使い方の例をいくつか挙げてみましたので、お試し下さいね。
また、最近は、「笑わない赤ちゃん」が増えているそうです。どうやって我が子をあやしたらいい
のかわからなくて、話しかけずにいるうち、情緒が未成熟になってしまう かわいそうな例です。
うまく話しかけられなくてお悩みのママも、パペットを手に話しかければ、もっとスムーズに幼児と
の会話がはずむかも・・・そんな願いも込めてお教えしています。
![]() まずは、名前を付けましょう
まずは、名前を付けましょう
お子さんと相談して、愛着の持てる名前をまず付け、名前で呼んで、擬人化し、特別な友達
として意識させてあげてください。クマ吉、クマちゃん、コロ、うさこ、ぴょん子、コン太、コンコン
なんでも、いいですよ。
![]() パペットをかたわらに置いて、絵本を読んであげましょう
パペットをかたわらに置いて、絵本を読んであげましょう
くまなら、くまの登場する絵本を、わざわざ選んで、何回も読んであげましょう。「○○に
も読んできかせてあげようね。」と側に置いて読み、終わったら、パペットに感想を言わせてみ
たり、お子さんにパペットから「どうだった?ぼくの活躍?」と、パペットの立場で、問いかけて
みたり。また、時には、お母さんが手にはめて、(出来るなら 少し声を変え、)パペットが読んで
いるようなシチュエーションで読み、興味を持たせたりも おもしろいかもしれません。
お母さんがそばにいないときに、パペットに本を読んであげているお子さんの姿を見つけたら、
しめたものてす。
![]() 親子げんかしたときにも使えます
親子げんかしたときにも使えます
反抗期が始まると、何かと親子の心がささくれ立つことも多いことでしょう。お子さんはケロッ
と していても、親の方がどうしても気持ちが治まらない。でも、いつまでもネチネチ根に持ってい
ては大人げないですよね。
そんな時も、パペットを手にして、「お母さんは怒っているけど、○○ちゃんのことが好きなん
だって。」と、口に出して言ってあげませんか?
しかるけれど、ちゃんと愛されているんだと、「すき」を言葉で伝える時も、パペットが間に入るこ
とで言いやすくなります。
いやいやをして、素直に言うことを聞かないときも、パペットを手にはめ、「○○ちゃんがやらない
んだったら、ぼくがやっちゃうよーー。」と、やってみてください。
パペットが、お母さんの言うことを聞く いい子を演じたり、逆に、悪い子を演じることで、子供の
気持ちを引きつけることができ、より円滑に親子関係を築くために役立ちますよ。
![]() 人形には性格を付け加えましょう
人形には性格を付け加えましょう
クマは、のんびり屋でまぬけ、うさぎは、優等生でしっかり者、キツネは、いたずらで、時に
悪い事もやる子。と言った性格がつけられていることが多いものです。
パペットを手に、お子さんに話しかけるときには、それぞれの性格にあった行動をとると、わか
りやすくなり、楽しく遊べます。
うさぎなら、「○○ちゃん、だめよ、そんなことしちゃ。」と、早口に、イライラたしなめる役柄。
「だめ!だめ!、あーー、ダメダメ。」と、せっかちに言われると、笑いながらつい従ってしまいま
すよね。
くまなら、「あーーー、○○ちゃん、いけないよぉー。」と、のんびりした口調で、やんわりたしな
めます。
きつねなら、わざと悪いことをして見せます。お子さんに「そんなことしちゃダメ!」と、優越感に
ひたれる注意をさせてあげることで、おこさんがいい手本になろうとして、行動を改めてくれます。
もちろん、一体のパペットが、いい子になったり、悪い子になって、お子さんと会話することで、
楽しく遊べますし、それを時には、しつけに利用することも出来るのです。
![]() 何体かそろったら、人形劇を楽しんでみましょう
何体かそろったら、人形劇を楽しんでみましょう
くま、うさぎ、きつねなど、絵本によく登場する動物を選んで制作しています。いくつかそろっ
たら、親子で役を決めて、物語を演じると楽しいですよ。幼児教材を見せたり、テキストを解いたり
することでは決して身に付かない、お子さんの表現力や情操面を引き延ばしてくれます。
![]() 親子クラブで使ってください
親子クラブで使ってください
一体だと寂しいけれど、何体か人形がそろうと、ボードビルが出来ますよ。
音楽に合わせて踊ってみると、お子さんたちも大喜び。お母さんたちで少し合わせる練習しをたら、
クリスマス会などで、お子さんたちを前にお披露目してみませんか?
もちろん、やりたいと言えば、お子さんたちも、次はやらせてあげてください。みんなで踊ると
楽しいですよ。
![]() 動物の出る絵本も紹介しているので、こちらからご覧下さいね。
動物の出る絵本も紹介しているので、こちらからご覧下さいね。